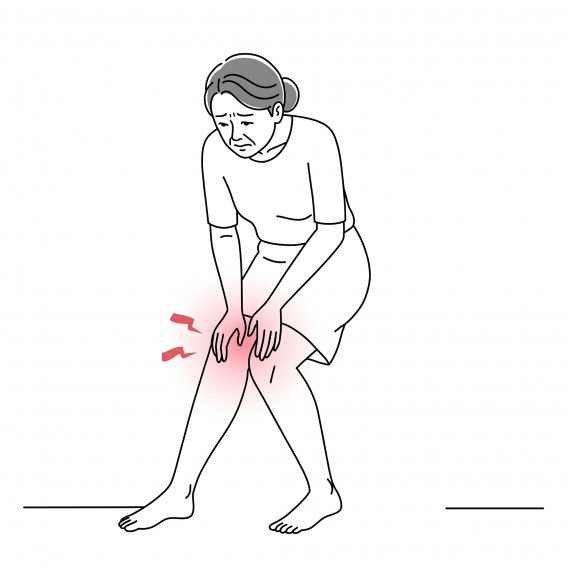耳鳴り
耳鳴りでお悩みの方へ:東西医学からのアプローチ
こんなお悩みはありませんか?
- ✓「キーン」「ジー」という音が耳の中で鳴り止まない
- ✓静かな場所に行くと特に耳鳴りが気になって集中できない
- ✓耳鳴りがあると同時に耳の閉塞感やめまいを感じることがある
- ✓疲れやストレスが溜まると耳鳴りが強くなる気がする
- ✓耳鳴りのせいで寝付きが悪く、睡眠の質が下がっている
- ✓病院で「特に治療法はない」と言われてしまった
耳鳴りは自分にしか聞こえない音が耳の中や頭の中で鳴り続ける症状です。日本人の10〜15%が経験すると言われるこの症状は、QOL(生活の質)を大きく下げる原因となっています。西洋医学では対症療法が中心となりがちですが、東洋医学では体全体のバランスから耳鳴りの原因にアプローチします。この記事では、西洋医学と東洋医学の両視点から耳鳴りの原因とメカニズムを解説し、当院の施術方法や自宅でできるセルフケアについてもご紹介します。
西洋医学的視点での耳鳴りの原因とメカニズム
西洋医学における耳鳴りの定義
西洋医学では、耳鳴り(医学的には「耳鳴症」または「Tinnitus」)を「外部からの音刺激がないにもかかわらず、音が知覚される現象」と定義しています。耳鳴りは症状であり、それ自体が病気ではなく、何らかの原因によって引き起こされる聴覚系の異常反応です。
耳鳴りには大きく分けて「他覚的耳鳴り」と「自覚的耳鳴り」があります。他覚的耳鳴りは医師も聴取できる実際の音(血管音など)によるもので、全体の約1%と非常に稀です。一方、自覚的耳鳴りは本人にしか聞こえない音で、大多数はこちらに分類されます。
主な原因
- 感音性難聴:加齢や騒音暴露による内耳の有毛細胞の損傷
- メニエール病:内耳の水分調節異常により、耳鳴り・めまい・難聴の症状が現れる
- 聴神経腫瘍:聴神経に発生する良性腫瘍で、片側性の耳鳴りを引き起こすことがある
- 中耳炎:中耳の炎症により耳鳴りが生じることがある
- 耳垢の蓄積:外耳道が耳垢で閉塞されることによる
- 薬剤性:アスピリン、一部の抗生物質、利尿剤などの副作用
- 頸部・顎関節の異常:筋肉の緊張や関節異常が耳に影響
- 代謝性疾患:糖尿病、高脂血症などによる血行不良
- ストレス・疲労:自律神経系の乱れによって増強
耳鳴りが発生するメカニズム
西洋医学では、耳鳴りの発生メカニズムについて主に以下のような考え方があります:
1. 内耳障害説:内耳の有毛細胞が損傷すると、異常な電気信号が発生し、これが脳に音として認識されます。加齢や騒音性難聴に多く見られます。
2. 中枢性メカニズム:脳の聴覚を処理する部分が過敏になり、通常なら気にならない小さな信号を「音」として強く認識してしまうようになります。これは、外からの刺激がなくなっても脳が独自に活動パターンを変化させる性質(脳の可塑性)によって起こると考えられています。簡単に言えば、脳が「音がないこと」に慣れず、自ら音を作り出してしまう状態です。
3. 聴覚フィルター機能の異常:通常、脳は不要な音を無視するフィルター機能を持っていますが、このフィルター機能が低下することで、本来は意識されない内部の音が知覚されるようになります。
耳鳴りの多くは、これらの要因が複合的に絡み合って起こると考えられています。
東洋医学的視点での耳鳴りの原因とメカニズム
東洋医学での耳鳴りの捉え方
東洋医学では、耳鳴りを「耳鳴(じめい)」と呼び、五臓六腑の機能バランスの乱れや気・血・水の異常によって起こると考えます。特に「腎」との関連が深いとされ、「腎は耳に開竅(かいきょう)する」(腎の状態が耳の機能に直接影響する)という考え方があります。
関連する経絡の説明
耳鳴りに関わる主な経絡には以下のものがあります:
- 腎経:耳の機能と直接関わる経絡で、腎の精気が不足すると耳鳴りが起こりやすい
- 三焦経:耳の周りを通り、耳の機能調節に関与する
- 胆経:頭部を巡る経絡で、肝胆の熱が上炎すると耳鳴りを引き起こすことがある
- 小腸経:耳の後方を通過し、聴覚機能に影響を与える
東洋医学の「証」による分類
腎精不足(じんせいふそく)
最も一般的な耳鳴りのタイプで、加齢や過労、慢性疾患による「腎の精気」の消耗によって起こります。特徴として、低く弱い耳鳴り(「ブーン」「ゴー」など)が持続し、めまい、腰膝の冷えや痛み、疲労感、記憶力低下なども伴うことがあります。
肝陽上亢(かんようじょうこう)
肝の陽気が過剰に上昇することで起こる耳鳴りです。ストレスや怒りが主な原因となります。特徴的なのは、高音の耳鳴り(「キーン」「ピー」など)で、頭痛、めまい、イライラ、顔面紅潮、不眠なども伴うことがあります。
痰湿上擾(たんしつじょうじょう)
体内に「痰」や「湿」が蓄積し、上昇して頭部を擾乱する状態です。不規則な食生活や過度の飲酒、湿気の多い環境などが原因となります。変動する音量の耳鳴りで、耳の閉塞感、めまい、頭重感、むくみなどを伴うことが特徴です。
気滞血瘀(きたいけつお)
気の流れが滞り、血液の循環も悪くなった状態です。ストレスや情緒不安定によって引き起こされます。脈打つような耳鳴りが特徴で、肩こり、胸部の圧迫感、月経異常(女性の場合)などを伴うことがあります。
腎陰虚火旺(じんいんきょかおう)
腎の陰液が不足し、相対的に火(熱)が亢進した状態です。慢性的な疲労、ストレス、加齢などが原因です。高音の断続的な耳鳴りに加え、のぼせ、ほてり、手足の熱感、寝汗、口渇などを伴います。
五臓六腑との関連性
東洋医学では、耳鳴りは特に以下の臓腑と関連があると考えられています:
- 腎:腎は先天の精を蔵し、骨や髄を養う働きがあり、耳は「腎の竅(穴)」とされ、腎の状態が直接耳の機能に影響する
- 肝:肝は血を蔵し、ストレスなどで肝の機能が乱れると、肝陽が上亢して耳鳴りの原因となる
- 脾:脾は水湿の代謝を担い、その機能低下は痰湿の生成につながり、耳鳴りを悪化させる
- 心:心は神志(精神活動)を司り、心の機能失調は不安やストレスを通じて耳鳴りに影響する
季節と環境の影響
東洋医学では、環境要因も耳鳴りの重要な影響因子と考えます:
- 冬:腎は冬に対応する臓器であり、冬の寒さは腎の機能に影響を与え、腎精不足タイプの耳鳴りが悪化しやすい
- 春:肝は春に対応する臓器で、春の変動しやすい気候は肝の機能に影響し、肝陽上亢タイプの耳鳴りが現れやすい
- 梅雨~夏:湿気が多い時期は痰湿が生じやすく、痰湿上擾タイプの耳鳴りが増加する傾向がある
- 気圧変化:気圧の変化は体内の気の流れに影響し、耳鳴りの増悪因子となることがある
西洋医学と東洋医学の耳鳴りに対するアプローチの比較
| 比較項目 | 西洋医学 | 東洋医学 |
|---|---|---|
| 原因の捉え方 | 内耳の有毛細胞の障害、聴覚神経系の異常、聴覚中枢の過敏など | 腎精不足、肝陽上亢、痰湿上擾など、気・血・水のバランス異常 |
| 診断方法 | 問診、聴力検査、平衡機能検査、画像診断(CT・MRI)、血液検査 | 望診(外観)、聞診(音)、問診(症状)、切診(脈・舌診) |
| 治療アプローチ | 原因疾患の治療、マスキング療法、薬物療法(血流改善薬、抗不安薬など)、認知行動療法 | 鍼灸、漢方薬、経絡調整、気功、食事療法 |
| 治療の焦点 | 症状の緩和、原因疾患の特定と治療、耳鳴りへの順応 | 全身のバランス調整、体質改善、根本原因への対処 |
| 予防的アプローチ | 騒音回避、ストレス管理、睡眠の確保、循環改善 | 食事調整、環境調整、情緒安定、適度な運動、腎精の養生 |
耳鳴りを放置するリスク
身体的リスク
- 難聴の進行:耳鳴りが内耳障害のサインである場合、適切な対処をしないと難聴が進行する可能性があります
- めまいの悪化:耳鳴りとめまいが合併している場合、放置すると平衡感覚の障害が悪化することがあります
- 重大疾患の見逃し:まれに、耳鳴りが聴神経腫瘍や血管性疾患など、重大な疾患のサインである場合があります
- 自律神経の乱れ:持続的な耳鳴りによるストレスは自律神経のバランスを崩し、他の身体症状を引き起こすことがあります
- 高血圧:耳鳴りによるストレスや不安が血圧上昇につながる可能性があります
精神的リスク
- 集中力低下:常に耳鳴りを気にすることで、仕事や勉強への集中力が著しく低下します
- 不安・抑うつ:「この音は一生続くのではないか」という不安から、抑うつ状態に陥ることがあります
- 睡眠障害:耳鳴りが特に静かな環境で目立つため、入眠困難や睡眠の質低下を引き起こします
- 社会的孤立:コミュニケーションの困難さや疲労感から社会活動を避け、孤立する可能性があります
- 生活の質の低下:上記の問題が複合的に作用し、全体的な生活の質が著しく低下します
耳鳴りを感じたら、「気にしなければ治る」と放置せず、適切な対処をすることが重要です。特に以下のような場合は、すぐに専門家に相談されることをおすすめします:
- 突然発症した強い耳鳴り(特に片側のみの場合)
- 耳鳴りに加えて難聴やめまいを伴う場合
- 脳神経症状(頭痛、顔面のしびれなど)を伴う耳鳴り
- 拍動性の耳鳴り(心拍と同期して鳴る)
- 耳鳴りによって日常生活に支障をきたしている場合
当院の耳鳴りに対する施術方法
施術の特徴
当院では、耳鳴りに対して東洋医学と西洋医学の知見を融合させた独自の施術を行っています。特に以下の点を重視しています:
- 優しい鍼灸治療:体質や証に合わせて鍼の本数を絞り、心地よい刺激で経絡の滞りを解消します
- 全身のバランス調整:耳だけでなく、首・肩・腰など全身の状態を診て、根本的な原因から改善を目指します
- 個別化された施術:東洋医学の「証」に基づいて、一人ひとりに合わせた施術プランを立てます
- 自律神経調整:ストレスや緊張による自律神経の乱れを整え、耳鳴りの悪化要因を軽減します
施術の流れ
- 丁寧な問診:耳鳴りの特徴(音の種類、発生時期、強さの変動など)や生活習慣、ストレス状況などをお伺いします
- 東洋医学的診断:脈診、舌診、腹診などを通じて体の状態を把握し、どの「証」に該当するかを見極めます
- 整体施術:頭蓋骨や頸椎、肩甲骨などの歪みを調整し、筋肉の緊張を緩和します
- 鍼灸治療:症状と体質に合わせたツボに鍼や灸で気血の流れを改善します
- アフターケア:施術後の注意点や自宅でのセルフケア方法をお伝えします
耳鳴りに効果的なツボ
当院では、耳鳴りのタイプに応じて例えば以下のようなツボを用います:
- 聴宮(ちょうきゅう):耳珠の前にあるツボで、耳の機能を直接調整します
- 翳風(えいふう):耳の後ろにあるくぼみのツボで、耳の血流を改善します
- 太谿(たいけい):足の内くるぶしの後ろにあるツボで、腎の機能を高めます
- 三陰交(さんいんこう):足首の内側にあるツボで、肝・脾・腎の三陰経が交わる重要なポイントです
- 百会(ひゃくえ):頭頂部中央にあるツボで、上昇する陽気を降ろす効果があります
- 風池(ふうち):後頭部の左右にあるツボで、首のこりや頭部の症状に効果があります
- 合谷(ごうこく):手の親指と人差し指の付け根にあるツボで、頭部の気の流れを調整します
これらのツボは手足に多く、施術中も比較的リラックスした状態で受けていただけます。また、お一人お一人の症状や体質に合わせて最適なツボを選択していきます。
耳鳴りに関するよくある質問(FAQ)
耳鳴りの症状の程度や期間、原因によって個人差がありますが、一般的には短期間(3ヶ月未満)の耳鳴りであれば5〜8回程度、慢性的な耳鳴り(1年以上)の場合は10〜15回程度の施術で変化が現れることが多いです。多くの患者様は3〜5回目の施術から「音の大きさが小さくなった」「気にならない時間が増えた」などの変化を実感されます。初回来院時に個別の施術計画をご提案させていただきます。
はい、密接な関係があります。首の筋肉の緊張は、頸椎を通る血管や神経を圧迫し、内耳への血流を悪くしたり、聴覚神経系に影響を与えたりすることで耳鳴りを引き起こす・悪化させることがあります。特に、ストレートネック(首の自然なカーブが失われた状態)や頭部前方位(首が前に出た姿勢)などの姿勢の問題がある方は、首こりと耳鳴りの両方に悩まされることが多いです。当院では耳鳴り治療の際に、首や肩のケアも重視し、全身のバランスを整える施術を行っています。
長期間続いている慢性耳鳴りでも改善する可能性は十分にあります。当院では、西洋医学的に「治らない」と言われることの多い慢性耳鳴りに対しても、東洋医学の「気・血・水」のバランス調整という視点からアプローチするため、多くの患者様に変化を実感いただいています。ただし、完全に音が消失するというよりは、「音が小さくなる」「気にならなくなる時間が増える」「音の質が変わる」といった形での改善が一般的です。「耳鳴りと共存しやすい状態」を目指しながら、徐々に体質改善を進めていくことで、長期的な改善が期待できます。
施術後は以下の点にご注意いただくとより効果的です:
- 施術当日の激しい運動や長時間のデスクワークを避ける
- 十分な水分補給を心がける(特に鍼灸治療後は体内の代謝が活発になります)
- アルコールや刺激物(カフェイン、辛いもの)の過剰摂取を控える
- 施術後24時間は特に大きな音を避け、耳を保護する
- 施術後に一時的に症状が強くなることがありますが(好転反応)、通常1〜2日で落ち着きます
はい、耳鳴りとめまいが同時に現れる場合、両者は関連している可能性が高いです。内耳には聴覚を担当する蝸牛と、平衡感覚を担当する三半規管があり、これらは非常に近接しているため、内耳の問題は両方の症状を引き起こすことがあります。メニエール病や前庭神経炎などの内耳疾患では、耳鳴り・めまい・難聴が同時に起こることが特徴です。東洋医学的には、これらの症状は多くの場合「腎精不足」や「肝陽上亢」の証と関連しており、総合的なアプローチが必要です。当院では耳鳴りとめまいの両方に対応した施術を行い、多くの患者様に改善を実感いただいています。
耳鳴り改善のための自宅でのセルフケア
姿勢の意識
姿勢の悪さは首や肩の緊張を通じて耳鳴りに影響します。以下の点に注意しましょう:
- デスクワーク中は背筋を伸ばし、画面の高さを目線と同じかやや下になるよう調整する
- スマートフォンを長時間見るときは、腕を持ち上げて目線に近づけ、首を下げない
- 長時間同じ姿勢を続けず、30分に1回程度は立ち上がって軽く体を動かす
- 就寝時は首への負担を軽減するため、高すぎず低すぎない枕を使用する
簡単ストレッチ
毎日続けられる簡単なストレッチをご紹介します:
- 首のストレッチ:ゆっくりと首を前後左右に倒し、緊張を緩めます(各方向10秒間保持、3回)
- 肩回し:肩を大きく前回し、後ろ回しします(各10回)
- 胸を開くストレッチ:両手を後ろで組み、胸を開くように肩甲骨を寄せます(15秒間保持、3回)
- 顎のストレッチ:顎を引き、首の後ろを伸ばします(10秒間保持、5回)
※痛みを感じる場合は無理せず、できる範囲で行ってください。
セルフツボ押し
自分で押せる耳鳴りに効果的なツボをご紹介します:
- 聴宮(ちょうきゅう):耳の前、顎関節のくぼみにあるツボを、指先で優しく円を描くようにマッサージします(各1分間)
- 翳風(えいふう):耳の後ろのくぼみにあるツボを、指先で押します(5秒間×3回)
- 太谿(たいけい):足の内くるぶしの後ろのくぼみを、反対の足の親指で押します(5秒間×3回)
- 風池(ふうち):後頭部の髪の生え際にある左右のくぼみを、両手の親指で同時に押します(5秒間×3回)
※強く押しすぎず、心地よい刺激を感じる程度に押してください。
耳のマッサージ
耳全体の血流を改善するマッサージも効果的です:
- 両手で耳全体を軽く包み込み、前後に10回ほど優しく動かす
- 耳たぶを親指と人差し指でつまみ、軽く引っ張りながら回す(10回程度)
- 耳の付け根から外側に向かって、指で耳の縁をなぞるように軽くつまむ(3回程度)
- 手のひらで耳を覆い、軽く圧迫と解放を繰り返す(10回程度)
生活習慣の改善
東洋医学の観点から、以下の点に注意することで耳鳴りの改善と予防に役立ちます:
- 食事:腎を養う黒い食材(黒豆、黒ごま、黒きくらげなど)や、ミネラル豊富な海藻類を適度に摂る
- 控えるべき食べ物:肝を熱させる辛いもの、揚げ物、アルコール、カフェインなどを控える
- 水分摂取:適度な水分補給を心がけ、特に白湯や薄めのハーブティーなどを意識して飲む
- 睡眠:十分な睡眠時間を確保し、特に23時〜3時の「腎の活動時間」にはしっかり眠る
- ストレス管理:瞑想や深呼吸などでリラックスする時間を持つ
- 音環境:騒音を避け、耳に優しい環境を整える(必要に応じてイヤープラグを使用)
- 適度な運動:ウォーキングやストレッチなど、血行を促進する軽い運動を習慣にする
サウンドマスキング
耳鳴りが特に気になるとき(就寝時など)には、以下のような環境音を活用することで注意をそらすことができます:
- 自然音(波の音、雨音、森の音など)
- ホワイトノイズ(ラジオのチューニングがずれたときのような音)
- 穏やかな音楽(クラシックや環境音楽など)
※音量は耳鳴りをちょうど覆い隠せる程度の小さめの音にし、長時間の使用は避けましょう。
耳鳴りのまとめと施術のご案内
耳鳴りは、西洋医学では内耳障害や聴覚神経系の異常として、東洋医学では気・血・水のバランスや五臓(特に腎と肝)の機能異常として捉えられます。どちらのアプローチも、それぞれに長所があり、当院ではこれらを組み合わせた総合的な施術を行っています。
「治らない」と言われがちな耳鳴りですが、症状の軽減や生活の質の向上は十分に可能です。特に東洋医学的アプローチは、体全体のバランスを整えることで耳鳴りの原因に多角的にアプローチできるという利点があります。
当院の特徴は、以下の点にあります:
- 一人ひとりの耳鳴りのタイプや体質に合わせた、オーダーメイドの施術プラン
- 優しい鍼灸治療と全身調整整体を組み合わせた効果的なアプローチ
- 自宅でのセルフケア指導による、長期的な改善サポート
- 耳鳴りに伴う不安やストレスにも配慮した精神面のケア
耳鳴りでお悩みの方は、ぜひ一度当院までご相談ください。丁寧な問診と診断を行い、最適な施術プランをご提案いたします。「この音とどう付き合っていけばいいのか分からない」という不安や悩みにも寄り添いながら、症状の改善を目指していきます。
ご予約・お問い合わせは、お電話またはウェブサイトから承っております。
お電話:072-622ー0134
受付時間:月・火・木・金 10:00~13:30 16:00~19:30
水・土 10:00~13:30
日曜・祝日 休み
567-0818
大阪府茨木市本町1-16本町8番館1階
(阪急茨木市駅から徒歩5分)
施術料 6600円(税込)
初診料 1100円(税込)
(前回の施術から2ヶ月以上空いた場合は1100円を頂いております)
※クレジットカード、QRコード払い等、各種キャッシュレス決済に対応しております。
ご予約はこちら
ネット予約:
LINEで予約:
電話で予約:
072-622-0134