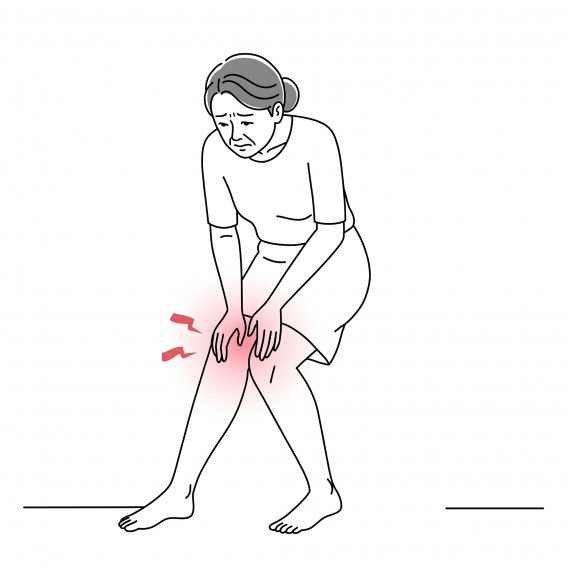野球肘
野球肘でお悩みの方へ
こんなお悩みはありませんか?
- 投球動作やスポーツ後に肘の内側や外側が痛む
- 肘を完全に伸ばせない、または曲げられない
- 肘を動かすとポキポキと音がする
- 手や指に痺れやしびれを感じることがある
- 投球フォームが崩れたり、球速や制球力が低下している
- 肘が腫れる、または熱を持つことがある
野球肘は、投球や打撃などの繰り返し動作によって肘に過度な負担がかかり、発症する障害です。特に成長期の子どもに多く見られますが、年齢を問わず野球やソフトボール、テニスなどの競技者に発症することがあります。
この記事では、野球肘の原因を西洋医学と東洋医学の両面から解説し、根本的な改善方法についてご紹介します。当院の鍼灸・整体がどのように野球肘の症状を緩和するのか、また自宅でできるセルフケアの方法についても詳しくお伝えしていきます。
西洋医学の視点から見た野球肘の原因とメカニズム
野球肘とは
西洋医学では、野球肘は「投球動作などの繰り返しによって肘関節に過度な負担がかかり、組織の損傷や炎症が生じた状態」と定義されています。野球肘は大きく分けて以下の3つのタイプに分類されます。
- 内側型:肘の内側に痛みが生じるタイプで、投球動作において牽引力(引っ張る力)が内側側副靭帯に過度にかかることで発生します。成長期の子どもでは内側上顆骨端線での障害(内側上顆骨端線離解)が起こりやすいです。
- 外側型:肘の外側に痛みが生じるタイプで、投球動作の加速期から減速期に肘関節が伸展する際、上腕骨小頭と橈骨頭が衝突することで発生します(離断性骨軟骨炎)。
- 後方型:肘の後方に痛みが生じるタイプで、投球動作のフォロースルー時に肘を完全に伸ばすことで、肘頭と上腕骨の間で衝突や絞扼が起こることで発生します(後方インピンジメント症候群)。
主な原因
- 過度な使用(オーバーユース):過剰な投球数や不十分な休息期間が最も一般的な原因です。
- 不適切な投球フォーム:特に腕だけで投げるフォームは肘に負担がかかります。
- 体の柔軟性・筋力不足:肩や背中、体幹の筋力不足や柔軟性の欠如があると、肘への負担が増加します。
- 成長期の特性:骨の成長と筋肉の発達のアンバランスが、成長期の子どもにおいて野球肘を引き起こしやすくします。
- 早期の専門化:一つのスポーツに早くから専念することで、同じ動作の繰り返しにより特定の部位に負担が集中します。
- 環境要因:気温(特に寒冷時)、不適切なウォームアップ、不適切な用具の使用なども関与します。
野球肘が発生するメカニズム
野球肘は以下のようなメカニズムで発生します:
- 投球動作の負荷:野球の投球動作は、特に加速期から減速期にかけて肘に大きな負荷がかかります。投手の場合、1球投げるだけで肘の内側側副靭帯には体重の約2倍もの力がかかるとされています。
- 微小損傷の蓄積:一度の投球では大きな問題を引き起こさなくても、繰り返し行われることで微小な損傷が蓄積し、やがて組織の修復能力を超えた損傷が生じます。
- 成長軟骨部の脆弱性:成長期の子どもでは、骨端線と呼ばれる軟骨部分が存在し、ここが成人に比べて力学的に弱いため、障害を受けやすくなっています。
- 筋疲労による代償動作:肩や体幹部の筋肉が疲労すると、本来それらが担うべき力学的役割を肘が代償しようとして、さらに肘への負担が増加します。
- 炎症反応と組織修復:負荷がかかった組織では炎症反応が起こり、適切な休息と処置があれば修復されますが、継続的な過負荷があると慢性的な障害に発展します。
主な症状
- 肘の痛み:投球動作中や投球後に肘の内側、外側、または後方に痛みを感じます。
- 可動域の制限:肘を完全に伸ばせない、または曲げられないことがあります。
- 腫れや熱感:肘関節が腫れたり、熱を持ったりすることがあります。
- 握力の低下:肘の痛みや機能障害により、握力が弱くなることがあります。
- パフォーマンスの低下:球速の低下、制球力の低下、投球フォームの崩れなどが見られることがあります。
- しびれや放散痛:尺骨神経が圧迫されると、小指側の手や前腕にしびれや痛みが放散することがあります。
西洋医学的なアプローチでは、まず急性期の炎症を抑えるための休息、アイシング、固定などが行われ、その後リハビリテーションとして段階的な筋力トレーニングやストレッチ、フォーム修正などが行われます。重症例では手術が必要になることもあります。
東洋医学の視点から見た野球肘の原因とメカニズム
東洋医学での野球肘の捉え方
東洋医学では、野球肘を「肘部の気血の滞り」や「経絡の障害」と捉えます。過度な使用により肘部の気と血の流れが滞り、痛みや機能障害が生じると考えられています。東洋医学では体を全体として診るため、肘の問題だけでなく、全身のバランスや気血の流れを重視します。
関連する経絡
野球肘に特に関連する経絡には以下のようなものがあります:
- 手の陽明大腸経(ようめいだいちょうけい):手の人差し指から肩へと流れる経絡で、肘の外側を通過します。外側型野球肘との関連が深いです。
- 手の少陽三焦経(しょうようさんしょうけい):手の薬指から肩へと流れる経絡で、肘の外側部を通ります。外側型野球肘に関与します。
- 手の太陰肺経(たいいんはいけい):肺から手の親指へと流れる経絡で、肘の内側を通ります。内側型野球肘と関連します。
- 手の厥陰心包経(けついんしんほうけい):胸部から手の中指へと流れる経絡で、肘の内側を通ります。内側型野球肘に関与します。
- 手の太陽小腸経(たいようしょうちょうけい):手の小指から肩へと流れる経絡で、肘の後方を通ります。後方型野球肘との関連があります。
東洋医学の「証」による分類
東洋医学では、野球肘を以下のような「証」(体質や症状のパターン)に分類します:
1. 気滞血瘀(きたいけつお)
特徴:過度な使用により気の流れが滞り、さらに血の流れも滞った状態です。
症状:鋭い痛み、肘の腫れ、熱感、運動時痛、夜間痛、触れると痛む。
改善方法:気の流れを促し、瘀血を除去する行気活血の治療が効果的です。
2. 風寒湿痹(ふうかんしつひ)
特徴:寒冷環境や湿度の高い環境で運動することで、風寒湿の邪が侵入した状態です。
症状:重だるい痛み、冷えると痛みが増す、動かしにくい、湿った環境で悪化する。
改善方法:温めて湿を取り除く温経散寒の治療が効果的です。
3. 肝腎不足(かんじんぶそく)
特徴:長期間のスポーツ活動や過労により、肝と腎の機能が低下した状態です。
症状:慢性的な痛み、疲れやすい、回復が遅い、夜間に痛みが増す、腰や膝にも症状がある。
改善方法:肝と腎を補う補肝腎の治療が効果的です。
4. 脾虚湿阻(ひきょしつそ)
特徴:脾の機能が低下し、水湿が体内に停滞した状態です。
症状:肘の腫れ、むくみ、だるさ、食欲不振、疲れやすい、雨の日や湿度の高い日に悪化する。
改善方法:脾の機能を高め、湿を除去する健脾利湿の治療が効果的です。
五臓六腑との関連性
東洋医学では、野球肘は以下の臓腑の機能と関連しています:
- 肝(かん):肝は筋や腱を司り、血を蓄える働きがあります。肝の機能低下は筋腱の強さや柔軟性に影響し、野球肘のリスクを高めます。
- 腎(じん):腎は骨を司り、成長発育に関わります。特に成長期の野球肘は腎の機能と密接に関連しています。
- 脾(ひ):脾は四肢の筋肉を養い、水湿を運化する役割があります。脾の機能低下は筋力低下や水湿の停滞を招き、肘の症状に影響します。
- 肺(はい):肺は気を全身に巡らせる役割があり、肺の機能低下は肘部の気の流れを妨げ、痛みや機能障害につながります。
- 心(しん):心は血脈を支配し、血の循環を司ります。心の機能低下は肘部の血行不良を招くことがあります。
季節と環境の影響
東洋医学では、季節や環境の変化も野球肘の症状に影響すると考えます:
- 春:風邪が強まる時期で、風による痹症(ひしょう)が起こりやすくなります。春の始めに急に活動量を増やすと、筋腱が対応しきれず症状が出やすくなります。
- 夏:暑さと湿気により湿熱が生じやすく、炎症症状が強くなることがあります。過度な汗による体液の損失も気血の不足につながります。
- 秋:乾燥しやすい時期で、体の潤いが不足すると筋腱の柔軟性が低下し、傷害を受けやすくなります。
- 冬:寒さにより気血の流れが鈍くなり、筋腱が硬くなりやすいため、ウォームアップが特に重要になります。寒さによる冷えは既存の症状を悪化させることがあります。
- 気候変動:急激な気候の変化は体のバランスを崩し、症状を誘発したり悪化させたりすることがあります。特に寒暖差が大きい日は注意が必要です。
東洋医学では、このように体質や環境、季節などの要因を総合的に考慮し、一人ひとりに合わせた治療方針を立てていきます。
西洋医学と東洋医学の比較
| 比較項目 | 西洋医学 | 東洋医学 |
|---|---|---|
| 病名・呼称 | 野球肘(内側型、外側型、後方型)、内側側副靭帯損傷、離断性骨軟骨炎など | 肘部の気滞血瘀、風寒湿痹、肝腎不足など |
| 原因の捉え方 | 過度な使用、不適切な投球フォーム、筋力不足、成長期の特性などによる靭帯や骨軟骨への機械的ストレス | 気血の滞り、経絡の障害、外邪(風寒湿)の侵入、五臓(特に肝腎脾)の機能低下 |
| 診断方法 | 身体所見、X線、MRI、超音波検査などの画像診断、スペシャルテスト(圧痛テスト、可動域テストなど) | 四診(望診・聞診・問診・切診)による証の判断、脈診、舌診、経絡の流れの確認 |
| 治療アプローチ | 安静、アイシング、消炎鎮痛剤、リハビリテーション(筋力強化、ストレッチ)、フォーム修正、重症例では手術 | 鍼灸治療、漢方薬、推拿(すいな)、体質や証に合わせた養生法、食養生 |
| 治療の焦点 | 局所的な組織損傷の治癒、炎症の軽減、機能回復、パフォーマンス向上 | 気血の流れの改善、経絡の通りを回復、体全体のバランスを整える、自然治癒力の向上 |
| 予防方法 | 投球制限、適切なウォームアップ、筋力トレーニング、正しい投球フォームの習得、オフシーズンの休息期間確保 | 日常的な経絡調整、季節に合わせた養生法、体質改善、気血の流れを良くする運動と休息のバランス |
| 再発予防 | 段階的な競技復帰プログラム、継続的な筋力トレーニング、投球メカニクスの改善 | 根本的な体質改善、五臓(特に肝腎)の機能強化、定期的な経絡調整 |
| 長所 | 科学的根拠に基づいた診断、急性期の炎症管理に効果的、重症例には手術などの根本的治療が可能 | 体全体を診る視点、個人の体質に合わせた治療、副作用が少ない、慢性症状にも効果的、予防医学の視点 |
西洋医学と東洋医学はそれぞれ異なる視点から野球肘にアプローチしますが、どちらも長所があります。当院では両方の知見を活かしながら、お一人おひとりに最適な治療を提供しています。
野球肘を放置するリスク
野球肘は「少し休めば治る」と軽視されがちですが、適切な対処をしないまま放置すると、短期的にも長期的にも様々な問題が生じる可能性があります。
身体的リスク
- 組織損傷の悪化:初期段階では微小な損傷でも、継続的な負荷により靭帯の完全断裂や骨軟骨の重度の損傷へと進行することがあります。
- 骨の変形:特に成長期の外側型野球肘では、離断性骨軟骨炎により上腕骨小頭が変形し、永続的な障害となることがあります。
- 関節可動域の制限:長期間放置すると、肘の伸展や屈曲が制限される拘縮が生じ、日常生活にも支障をきたす可能性があります。
- 神経障害:尺骨神経が圧迫され続けると、手や指のしびれ、握力低下、筋萎縮などの神経症状が慢性化することがあります。
- 早期の関節症:野球肘によって肘関節の不均等な負荷が続くと、将来的に変形性関節症のリスクが高まります。
- リハビリ期間の長期化:早期に適切な治療を受けず症状が悪化すると、競技復帰までの期間が大幅に延長します。
スポーツパフォーマンスへの影響
- 投球能力の低下:痛みや機能障害により、球速や制球力が低下し、競技パフォーマンスが低下します。
- 代償動作の発生:肘の痛みを避けるために不自然なフォームになり、さらに肩や体幹など他の部位に負担がかかる悪循環が生じます。
- 競技継続の困難:症状が進行すると、野球などの投球動作を含むスポーツの継続が困難になる場合があります。
- 選手生命の短縮:適切な治療とケアがなければ、選手としてのキャリアが短くなる可能性があります。
精神的・社会的リスク
- 競技参加の制限:長期間の競技休止により、チームでの役割や居場所が失われる可能性があります。
- 自己肯定感の低下:特に子どもや青少年の場合、スポーツができないことが自信の喪失につながることがあります。
- 将来の進路への影響:高校生や大学生の場合、スポーツ推薦や進学、スカウト機会などに影響する可能性があります。
- 慢性痛によるストレス:長期間の痛みは精神的ストレスや不安、抑うつ感を引き起こすことがあります。
早期対処の重要性
野球肘は、早期に適切な対処を行うことで改善の可能性が高まります。早期対処には以下のようなメリットがあります:
- 症状が軽度なうちに治療を始めることで、組織の完全な回復が期待できます
- リハビリ期間が短縮され、早期に競技復帰できる可能性が高まります
- 手術などの侵襲的な治療が必要になるリスクを減らせます
- 正しい投球フォームやコンディショニング方法を早い段階で学ぶことで、再発防止につながります
- 長期的な関節機能の保全により、スポーツ寿命が延びる可能性があります
肘の痛みや違和感を感じたら、「様子を見る」「痛み止めで乗り切る」などの対処ではなく、専門家による適切な評価と治療を受けることが重要です。当院では、早期発見・早期治療を重視し、野球肘の症状に迅速に対応しています。
当院の野球肘施術方法
当院では、東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた独自のアプローチで野球肘の根本改善を目指します。一人ひとりの症状や体質に合わせたオーダーメイドの施術を行い、単に痛みを取り除くだけでなく、再発予防までを視野に入れた総合的なケアを提供します。
施術の特徴
- 手足のツボを使った鍼灸治療:身体に負担の少ない施術で、肘から離れた部位のツボも活用して全身の気血のバランスを整えます。
- 東洋医学的診断に基づくアプローチ:脈診や舌診などの東洋医学的診断を行い、あなたの「証」を見極めた施術を行います。
- 整体:肘だけでなく、肩や背中、骨盤など全身のバランスを整えることで、肘への負担を減らします。
- スポーツ動作の分析と指導:投球フォームなどの動作分析を行い、問題点の改善につなげます。
- 段階的リハビリプログラム:症状の回復に合わせた段階的な運動プログラムを提案し、安全な競技復帰をサポートします。
施術の流れ
- 詳細な問診:症状の経過、スポーツ歴、練習環境、既往歴などを詳しくお聞きします。
- 東洋医学的診断:脈診・舌診・望診などを通じて、あなたの体質や「証」を判断します。
- 西洋医学的検査:関節可動域、筋力、特殊テストなどで肘の状態を詳しく評価します。
- 整体施術:全身のバランスを整える優しい整体施術を行います。
- 鍼灸治療:あなたの体質や症状に合わせたツボに鍼をし、必要に応じてお灸を行います。
- アフターケア:施術後の注意点や、自宅でできるセルフケア方法についてアドバイスします。
野球肘に効果的なツボ
当院では以下のようなツボを用いて、お一人おひとりの症状に合わせた治療を行います:
手足のツボ(遠隔治療)
- 合谷(ごうこく):手の親指と人差し指の付け根にあるツボで、全身の気の流れを改善し、鎮痛効果があります。
- 手三里(てさんり):前腕の外側にあるツボで、肘の痛みの緩和と腕の筋力強化に効果があります。
- 曲池(きょくち):肘を曲げたときにできるシワの外側の端にあるツボで、肘の痛みや腫れに効果的です。
- 足三里(あしさんり):膝の下外側にあるツボで、全身の気を補い、疲労回復に効果があります。
- 太衝(たいしょう):足の甲の親指と人差し指の付け根の間にあるツボで、肝の機能を高め、筋腱の緊張を和らげます。
これらのツボはあくまで一例で、実際の施術では、お一人おひとりの体質や証、症状の程度に合わせて最適なツボを選択し、施術を行います。
競技復帰までのサポート
当院では、単に痛みを取り除くだけでなく、安全に競技復帰できるよう段階的なサポートを行います:
- 急性期(休息期):痛みと炎症の軽減を優先し、投球動作の休止と適切なケアを行います。
- 回復期(リハビリ期):筋力強化やストレッチなどの段階的なエクササイズを導入し、肘の機能回復を図ります。
- 機能向上期:肘だけでなく、肩や体幹の筋力強化も含めた総合的なコンディショニングを行います。
- 投球再開期:段階的な投球プログラムを指導し、徐々に投球数や強度を増やしていきます。
- 競技復帰期:実戦形式での動作確認と、再発防止のための継続的なケア方法を指導します。
当院の施術は痛みを感じにくい優しいものですので、小学生から高齢者まで、幅広い年齢層の方に安心して受けていただけます。野球肘でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
野球肘に関するよくある質問(FAQ)
野球肘の治療期間は、症状の重症度や種類(内側型、外側型、後方型)、年齢、これまでの経過などによって個人差があります。一般的な目安としては以下のようになります:
- 軽度の症状:2〜4週間程度の休息と適切なケアで改善することが多いです。
- 中程度の症状:1〜3ヶ月程度の治療期間が必要で、段階的なリハビリプログラムを経て競技復帰を目指します。
- 重度の症状:3〜6ヶ月以上かかることもあり、特に離断性骨軟骨炎などの場合は長期間の治療とリハビリが必要です。
当院では、初回の診断時に症状の状態を詳しく評価し、おおよその治療期間と回復プロセスについてご説明いたします。早期発見・早期治療が最も治療期間を短縮する鍵となりますので、肘に違和感を感じたらすぐにご相談ください。
お子さんの野球肘予防のために親ができることはたくさんあります:
- 投球数の管理:年齢に応じた適切な投球数を守るよう指導者と連携しましょう。一般的に、9-10歳は1日50球まで、11-12歳は75球まで、13-14歳は75-100球までが目安です。
- 十分な休息期間の確保:連日の投球や、複数チームでのプレーによる過度な負担を避けましょう。週に2日以上は投球を休む日を設けることが推奨されています。
- 適切なウォームアップの奨励:練習前の十分なウォームアップと、練習後のクールダウンの重要性をお子さんに教えましょう。
- 痛みのサインに注意:「少し我慢すれば大丈夫」という考えは危険です。肘の痛みを訴えたら、すぐに投球を中止し、専門家に相談しましょう。
- 多様なスポーツ経験の奨励:一年中同じスポーツだけでなく、オフシーズンには異なるスポーツを楽しむことで、特定の部位への継続的な負担を減らし、総合的な運動能力を高めることができます。
当院では、お子さんの成長段階に合わせた予防プログラムのアドバイスも行っていますので、お気軽にご相談ください。
野球肘の完治の見込みは、症状の種類や重症度、治療の早さ、治療法、そして患者さん自身の回復力によって異なります。
内側型野球肘(内側側副靭帯の損傷)は、適切な休息とリハビリにより、多くの場合良好な回復が期待できます。外側型(離断性骨軟骨炎)は、早期発見と適切な治療が特に重要で、放置すると骨片の遊離や関節変形などの合併症リスクが高まります。
当院の東洋医学と西洋医学を組み合わせたアプローチでは、単に症状を抑えるだけでなく、体全体のバランスを整え、再発しにくい体づくりを目指します。適切な治療と、その後の継続的なセルフケア、そして投球フォームの改善や筋力トレーニングなどの予防策を講じることで、多くの患者さんが元のパフォーマンスレベルに戻ることができています。
はい、鍼治療は適切な方法で行えば子どもにも安全に適用できます。当院では、お子さんの年齢や体格、不安の程度に合わせて施術方法を調整しています。
子どもへの鍼治療では、特に以下のような工夫をしています:
- 非常に細い鍼を使用し、手足のツボを中心とした身体に負担の少ない施術を行います
- 場合によっては、鍼を皮膚に接触させるだけの接触鍼や、皮膚に刺さない小児鍼を使用することもあります
- 施術前に十分な説明を行い、お子さんの不安を取り除くよう心がけています
痛みについては、使用する鍼が非常に細いため、多くの方が「蚊に刺されたような軽い感覚」か「ほとんど感じない」と表現されます。痛みに敏感なお子さんには、まず保護者の方に体験していただいて、その様子を見てもらうこともできます。お子さんの治療に関して心配な点があれば、お気軽にご相談ください。
施術後は以下の点にご注意いただくと、効果を最大限に引き出すことができます:
- 安静の確保:施術当日は激しい運動や投球動作を避け、肘を休ませてください
- 水分摂取:十分な水分を摂取して、体内の循環を促進させましょう
- 患部の保護:症状や施術内容によっては、一時的なアイシングや保温が必要な場合があります(個別に指示します)
- セルフケア:指導されたストレッチやエクササイズを継続的に行いましょう
- 症状の観察:施術後の変化や症状の推移を観察し、次回の施術時に報告してください
また、稀に施術後に一時的な違和感や軽い痛みを感じることがありますが、これは体が調整されていく過程で起こる「好転反応」の一種で、通常は24〜48時間以内に収まります。気になる症状がある場合は、遠慮なく院長にご相談ください。
野球肘改善のための自宅でのセルフケア
野球肘の改善には、施術と併せて日常生活での取り組みも重要です。以下のセルフケア方法を継続的に行うことで、症状の緩和と再発防止につながります。
急性期(痛みがある時期)のケア
- RICE処置:Rest(休息)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の原則に従い、急性期の炎症を抑えます。特に投球動作は必ず休止してください。
- 適切なアイシング:痛みや腫れがある場合は、15〜20分間のアイシングを1日に数回行います。直接氷を肌に当てず、タオルなどで包んでください。
- 可動域を維持する軽いストレッチ:痛みのない範囲で、肘の曲げ伸ばしを優しく行い、関節の固まりを防ぎます。
- 姿勢の意識:デスクワークやスマホ使用時など、日常生活での肘や腕の使い方に注意し、不必要な負担を避けましょう。
回復期のストレッチとエクササイズ
痛みが落ち着いてきたら、以下のようなストレッチとエクササイズを段階的に取り入れていきましょう。いずれも痛みを感じない範囲で行うことが重要です:
- 前腕のストレッチ:
- 手のひらを上に向け、もう片方の手で指を後ろに引っ張るストレッチ(20秒間×3回)
- 手のひらを下に向け、もう片方の手で指を後ろに引っ張るストレッチ(20秒間×3回)
- リストカール:軽い重り(初めは500gくらい)を持ち、手首を上下に動かす運動(10回×3セット)
- プロネーション/スピネーション:前腕を回内・回外させる運動で、肘の安定性を高めます(各方向10回×3セット)
- グリップ強化:握力ボールやハンドグリッパーを使った握力トレーニング(10回×3セット)
機能回復期・スポーツ復帰期のトレーニング
- 肩甲骨周りの強化:
- Yエクササイズ:腕をY字型に上げるトレーニング
- Tエクササイズ:腕をT字型に広げるトレーニング
- Wエクササイズ:腕をW字型に曲げるトレーニング
- ローテーターカフの強化:肩の回旋筋群を鍛えるトレーニングで、外旋・内旋運動を行います。チューブやゴムバンドを使うとより効果的です。
- 体幹トレーニング:プランクやサイドプランクなどで、体幹の安定性を高め、投球時の力の伝達を改善します。
- 下半身の強化:スクワットやランジなどで下半身の筋力を高め、投球動作時の下半身主導の力の伝達を促進します。
日常生活での予防策
- 適切なウォームアップ:運動前には必ず十分なウォームアップを行い、徐々に体を動かす強度を上げていきましょう。
- 投球数の管理:年齢や体力に適した投球数を守り、過度な使用を避けましょう。
- 定期的な休息:連日の投球練習を避け、週に最低2日は投球を休みましょう。年間を通じても、2〜3ヶ月は投球を完全に休止する期間を設けることが推奨されています。
- 正しい投球フォーム:効率的で肘に負担の少ない投球フォームを身につけ、定期的にコーチや専門家にチェックしてもらいましょう。
- 栄養と水分:十分な栄養摂取と水分補給は、筋肉や腱の健康を維持し、回復を促進します。特にタンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂りましょう。
- 適切な睡眠:質の良い睡眠は回復と成長に不可欠です。特に成長期のアスリートは十分な睡眠時間を確保しましょう。
ツボ押し
自分でできるツボ押しも効果的です。以下のツボを親指や人差し指で3〜5秒間押し、緩めるを10回程度繰り返しましょう:
- 合谷(ごうこく):親指と人差し指の付け根の間にあるツボです。全身の気の流れを改善し、鎮痛効果があります。
- 手三里(てさんり):肘を曲げたとき、肘横から指幅4本下の前腕外側にあるツボです。腕の痛みや疲労回復に効果があります。
- 曲池(きょくち):肘を曲げたときにできる肘関節外側のシワの端にあるツボです。肘の痛みや腫れに効果的です。
- 足三里(あしさんり):膝の下外側、すねの骨の外側にあるツボです。全身の気を補い、疲労回復に効果があります。
これらのセルフケアを日常生活に取り入れることで、施術の効果を高め、野球肘の症状改善と再発防止につながります。ただし、これらのエクササイズは一般的なガイドラインであり、症状の程度や回復段階によって適切なエクササイズは異なります。当院では、お一人おひとりの状態に合わせたセルフケアプログラムをご提案いたします。
野球肘のまとめと施術のご案内
野球肘の要約
野球肘は、投球動作などの繰り返しによって肘関節に過度な負担がかかり、痛みや機能障害を引き起こす障害です。内側型、外側型、後方型の3つのタイプがあり、特に成長期の子どもに多く見られますが、年齢を問わず発症する可能性があります。
西洋医学では主に過度な使用や不適切なフォーム、筋力不足などが原因と考えられ、東洋医学では経絡の障害や気血の滞り、五臓(特に肝腎)の機能低下が関与していると捉えます。
野球肘を放置すると、組織損傷の悪化、慢性的な痛み、競技パフォーマンスの低下、さらには長期的な関節機能障害など、様々なリスクがあります。早期発見・早期治療が重要であり、適切なケアと予防策を講じることで、多くの場合症状の改善と競技復帰が可能です。
当院のアプローチの特徴
当院では、野球肘に対して以下のようなアプローチを行っています:
- 東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた総合的な施術
- 一人ひとりの体質や症状に合わせたオーダーメイドの治療計画
- 手足のツボを使った鍼灸治療による身体に負担の少ない施術
- 肘だけでなく、肩や体幹など全身のバランスを整える整体
- 段階的な復帰プログラムによる再発予防と競技パフォーマンス向上のサポート
- 症状の緩和だけでなく、根本的な体質改善と再発防止を目指した施術
多くの患者様から「痛みが軽減した」「投球動作が楽になった」「球速や制球力が向上した」「再発しなくなった」といったお声をいただいております。野球肘でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご予約・お問い合わせ
野球肘の症状でお悩みの方は、ぜひ当院までご連絡ください。初回のカウンセリングで丁寧にお話を伺い、最適な施術プランをご提案いたします。小さなお子様から高齢の方まで、幅広い年齢層の方に対応しています。
【住所】
567-0818
大阪府茨木市本町1-16本町8番館1階
(阪急茨木市駅から徒歩5分)
【お電話】
072-622ー0134
【受付時間】
月・火・木・金 10:00~13:30 16:00~19:30
水・土 10:00~13:30
日曜・祝日 休み
野球肘は早期発見・早期治療が重要です。痛みや違和感を感じたら、無理をせずに専門家に相談することをおすすめします。当院では、あなたの野球肘の根本改善をサポートし、スポーツ復帰をお手伝いいたします。
施術料
恥骨の痛みでお悩みの方へ
こんなお悩みはありませんか?
- 妊娠中や産後に恥骨部分に痛みが出るようになった
- 歩くときや階段の昇降時に恥骨が痛む
- 起き上がりや寝返りをするときに恥骨周辺が痛む
- 足を大きく開いたり、片足立ちをすると恥骨が痛む
- スポーツ中や運動後に恥骨周辺に痛みを感じる
- 恥骨から太ももの内側にかけて痛みやしびれがある
恥骨の痛みは、恥骨結合部やその周辺の筋肉、靭帯に炎症や負担がかかることで発生する症状です。特に妊娠中や産後の女性に多く見られますが、スポーツ選手や日常生活での姿勢の問題により男性にも起こることがあります。
この記事では、恥骨の痛みの原因を西洋医学と東洋医学の両面から解説し、根本的な改善方法についてご紹介します。当院の鍼灸・整体がどのように恥骨の痛みを緩和するのか、また自宅でできるセルフケアの方法についても詳しくお伝えしていきます。
西洋医学の視点から恥骨の痛みの原因とメカニズム
恥骨の痛みとは
西洋医学では、恥骨の痛みは「恥骨結合部の機能不全や炎症によって引き起こされる痛み」と定義されています。恥骨結合は左右の恥骨をつなぐ軟骨性の関節で、通常は非常に動きの少ない関節ですが、妊娠中のホルモンの影響や外傷により不安定になることがあります。
主な原因
- 妊娠・出産関連:妊娠中に分泌されるリラキシンなどのホルモンにより靭帯が緩み、恥骨結合部が不安定になります。また、胎児の成長により骨盤への負荷が増加します。
- スポーツ外傷:サッカー、ランニング、体操など、恥骨周辺に強い負荷がかかるスポーツで発生することがあります。
- 筋肉の不均衡:腹筋、背筋、骨盤底筋群のバランスが崩れることで、恥骨結合部に過度な負担がかかります。
- 姿勢の問題:骨盤の前傾や後傾、左右の歪みにより恥骨部分への負荷が増加します。
- 外傷:転倒や交通事故などによる骨盤周辺への直接的な外力により損傷することがあります。
- 感染症:稀に恥骨結合部の感染症(恥骨結合炎)により痛みが生じることがあります。
恥骨の痛みが発生するメカニズム
恥骨の痛みは以下のようなメカニズムで発生します:
- 妊娠中のホルモンの影響や外力により、恥骨結合部の軟骨や靭帯に炎症や微細損傷が生じます
- 恥骨結合部の不安定性により、周辺の筋肉(腹直筋、内転筋群、骨盤底筋)が過度に緊張します
- 筋肉の緊張により血流が悪化し、痛みを感じる侵害受容器が刺激されます
- 疼痛により動作を避けるようになると、さらに筋力低下や関節の可動域制限が生じ、症状が悪化する悪循環に陥ります
- 慢性化すると、中枢神経系での痛みの処理が変化し、軽微な刺激でも強い痛みを感じるようになることがあります
主な症状
- 恥骨部の痛み:恥骨結合部を中心とした局所的な痛みで、触ると痛みが増すことがあります。
- 放散痛:恥骨から太ももの内側、下腹部、腰部への痛みの放散が見られることがあります。
- 歩行時痛:歩く際、特に足を前に出すときや階段昇降時に痛みが強くなります。
- 起立・座位での痛み:立ち上がりや座るときに痛みが生じることがあります。
- 寝返り時の痛み:夜間の寝返りや起き上がり時に強い痛みを感じることがあります。
- 筋力低下:痛みにより活動量が減少し、骨盤周辺の筋力が低下することがあります。
西洋医学的なアプローチでは、安静、物理療法、運動療法、場合によっては薬物療法が用いられますが、根本的な改善には筋力強化と姿勢改善が重要とされています。
東洋医学の視点から恥骨の痛みの原因とメカニズム
東洋医学での恥骨の痛みの捉え方
東洋医学では、恥骨の痛みを「気血の滞り」や「経絡の不調」により起こる状態と捉えます。恥骨周辺は生殖器に関わる重要な部位であり、腎や肝の機能と密接に関連すると考えられています。特に妊娠・出産期は腎の精気が大きく消耗するため、この時期の恥骨の痛みは腎虚との関連が深いとされています。
関連する経絡
恥骨の痛みに特に関連する経絡には以下のようなものがあります:
- 任脈(にんみゃく):身体の前面中央を通る経絡で、恥骨から生殖器、下腹部の機能に関わります。
- 足の厥陰肝経(けついんかんけい):恥骨周辺を通り、生殖器機能や筋腱の働きに関連します。
- 足の少陰腎経(しょういんじんけい):腎の機能を担う経絡で、骨や髄、生殖機能に関わります。
- 足の太陰脾経(たいいんひけい):下腹部から恥骨周辺を通り、筋肉の働きや水分代謝に関連します。
- 衝脈(しょうみゃく):下腹部の奇経八脈の一つで、生殖機能や血の巡りに関わります。
東洋医学の「証」による分類
東洋医学では、恥骨の痛みを以下のような「証」(体質や症状のパターン)に分類します:
1. 腎虚(じんきょ)
特徴:妊娠・出産、加齢、過労により腎の精気が不足した状態です。
症状:恥骨周辺の鈍い痛み、腰痛、足腰のだるさ、頻尿、むくみ、疲れやすい、冷え症。
改善方法:腎を補う食材(黒ゴマ、クルミ、山芋など)や補腎の漢方薬、温める鍼灸治療が効果的です。
2. 肝鬱気滞(かんうつきたい)
特徴:ストレスや感情の抑制により肝の気の流れが滞った状態です。
症状:恥骨周辺の刺すような痛み、痛みの場所が移動する、イライラ、ため息、生理不順、胸の張り。
改善方法:肝の気の流れを改善する食材(柑橘類、香味野菜など)や疏肝解鬱の漢方薬、鍼灸治療が効果的です。
3. 血瘀(けつお)
特徴:血液の循環が悪くなり、血の滞りが生じた状態です。
症状:恥骨周辺の固定した刺すような痛み、夜間に痛みが増す、皮膚の色が暗い、生理時の血塊。
改善方法:血の流れを改善する食材(山査子、紅花茶など)や活血化瘀の漢方薬、鍼灸治療が効果的です。
4. 寒湿(かんしつ)
特徴:冷えと湿気が体内に侵入し、気血の流れを妨げている状態です。
症状:恥骨周辺の重だるい痛み、冷えると痛みが悪化、むくみ、下痢しやすい、関節の重い感じ。
改善方法:体を温め湿気を取り除く食材(生姜、シナモン、ハトムギなど)や温経散寒の漢方薬、温灸治療が効果的です。
5. 脾虚(ひきょ)
特徴:消化機能の低下により気血の生成が不足した状態です。
症状:恥骨周辺の鈍い痛み、疲れやすい、食欲不振、下痢しやすい、顔色が悪い、手足のむくみ。
改善方法:脾胃を補う食材(山芋、カボチャ、小豆など)や補気健脾の漢方薬、鍼灸治療が効果的です。
五臓六腑との関連性
東洋医学では、恥骨の痛みは主に以下の臓腑の機能と関連しています:
- 腎(じん):生殖機能や骨・髄を支配し、恥骨周辺の骨格や筋肉の健康に重要な役割を果たします。
- 肝(かん):筋腱を支配し、気の流れを調整します。肝の機能低下は筋肉の緊張や痛みを引き起こします。
- 脾(ひ):筋肉を支配し、水分代謝に関わります。脾の機能低下は筋力低下やむくみを引き起こします。
- 心(しん):血液循環を支配し、恥骨周辺の血流に影響します。
季節と環境の影響
東洋医学では、季節や環境の変化も恥骨の痛みに影響すると考えます:
- 冬:寒さにより腎の機能が低下しやすく、恥骨周辺の痛みが悪化しやすい季節です。
- 梅雨時期:湿気により脾の機能が低下し、むくみや重だるい痛みが増すことがあります。
- 春:肝の気が上昇する時期で、ストレスによる肝鬱気滞の症状が悪化しやすくなります。
- 冷房の効いた環境:長時間の冷えにより寒湿が体内に侵入し、痛みが増すことがあります。
東洋医学では、このように体質や環境、季節などの要因を総合的に考慮し、一人ひとりに合わせた治療方針を立てていきます。
西洋医学と東洋医学の比較
| 比較項目 | 西洋医学 | 東洋医学 |
|---|---|---|
| 原因の捉え方 | 恥骨結合部の機能不全、ホルモンの影響、筋肉の不均衡、外傷 | 気血の滞り、腎や肝の機能低下、経絡の不調 |
| 診断方法 | X線検査、MRI、CT、理学的検査、触診 | 四診(望診・聞診・問診・切診)による証の判断、脈診、舌診 |
| 治療アプローチ | 安静、物理療法、運動療法、薬物療法、場合によっては手術 | 鍼灸治療、漢方薬、推拿(すいな)、体質や証に合わせた養生法 |
| 治療の焦点 | 炎症の抑制、筋力強化、構造的安定性の回復 | 気血の流れの改善、腎肝の機能強化、体全体のバランス調整 |
| 妊娠期への対応 | 薬物療法に制限があり、主に物理療法や運動療法が中心 | 妊娠期に安全な鍼灸治療や食養生で対応可能 |
| 予防の考え方 | 筋力強化、姿勢改善、適切な体重管理 | 体質に合わせた養生法、腎肝の機能強化、未病の段階からの対応 |
| 再発予防 | 継続的な運動療法、生活習慣の改善 | 体質改善による根本的な再発予防、季節に合わせた養生 |
西洋医学と東洋医学は、それぞれ異なるアプローチで恥骨の痛みに対処しますが、どちらも長所があります。当院では両方の知見を活かしながら、お一人おひとりに最適な治療を提供しています。
恥骨の痛みを放置するリスク
恥骨の痛みは「一時的なもの」と軽視されがちですが、適切な対処をしないまま放置すると、様々な問題が生じる可能性があります。
身体的リスク
- 慢性疼痛への移行:急性の痛みが慢性化し、日常的に痛みを感じる状態になるリスクがあります。
- 歩行障害:痛みにより正常な歩行が困難になり、跛行(びっこ)や歩行速度の低下が生じます。
- 筋力低下:痛みを避けるために活動量が減ると、骨盤周辺の筋力が著しく低下します。
- 姿勢の悪化:痛みをかばう姿勢を続けることで、骨盤の歪みや脊柱の変形が進行する可能性があります。
- 他部位への影響:恥骨の痛みをかばうことで、腰痛、股関節痛、膝痛などの二次的な症状が出現することがあります。
- 関節拘縮:長期間の痛みにより股関節や仙腸関節の可動域が制限される可能性があります。
- 妊娠・出産への影響:女性の場合、将来の妊娠・出産時に症状が悪化するリスクがあります。
精神的・社会的リスク
- 生活の質の低下:痛みにより日常生活動作が制限され、生活の質が大幅に低下します。
- 睡眠障害:寝返りや起き上がり時の痛みにより、良質な睡眠がとれなくなります。
- 不安とストレス:「いつまで痛みが続くのか」という不安や、活動制限によるストレスが増加します。
- 社会活動への影響:仕事や家事、育児への影響により、社会的役割を果たすことが困難になることがあります。
- 自己効力感の低下:「何をしても良くならない」という無力感から、自己肯定感が低下することがあります。
- 人間関係への影響:痛みによるイライラや活動制限により、家族や友人との関係に支障をきたすことがあります。
早期対処の重要性
恥骨の痛みは、早期に適切な対処を行うことで改善の可能性が高まります。早期対処には以下のようなメリットがあります:
- 炎症が慢性化する前に改善できる
- 筋力低下や関節拘縮を予防できる
- 代償的な姿勢変化による二次的症状を予防できる
- 日常生活への影響を最小限に抑えられる
- 治療期間を短縮できる可能性がある
- 将来の妊娠・出産時のリスクを軽減できる
恥骨周辺の痛みや違和感を感じたら、「そのうち良くなる」と放置せず、早めに専門家に相談することをおすすめします。
当院の恥骨の痛み施術方法
当院では、東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた独自のアプローチで恥骨の痛みの根本改善を目指します。一人ひとりの症状や体質に合わせたオーダーメイドの施術を行い、痛みの軽減と機能回復を促進します。
施術の特徴
- 手足のツボを使った鍼灸治療:身体に負担の少ない施術で、初めての方でも安心して受けられます。
- 東洋医学的診断に基づくアプローチ:脈診や舌診などの東洋医学的診断を行い、あなたの「証」を見極めた施術を行います。
- 妊娠期にも安全な施術:妊娠中の恥骨の痛みにも対応できる安全な鍼灸治療を提供します。
- 骨盤調整:骨盤の歪みや不安定性を改善する優しい整体施術を行います。
- 全身調整:恥骨の痛みの原因となる全身のバランスを整え、根本的な改善を目指します。
施術の流れ
- 問診:恥骨の痛みの症状や生活習慣、既往歴などを詳しくお聞きします。
- 東洋医学的診断:脈診・舌診・腹診などを通じて、あなたの体質や「証」を判断します。
- 整体施術:必要に応じて、骨盤や全身のバランスを整える優しい整体施術を行います。
- 鍼灸治療:あなたの体質や症状に合わせたツボに優しく鍼をし、必要に応じてお灸を行います。
- アフターケア:施術後の注意点や、自宅でできるケア方法についてアドバイスします。
恥骨の痛みに効果的なツボ
当院では以下のようなツボを用いて、お一人おひとりの症状に合わせた治療を行います:
手足のツボ(遠隔治療)
- 三陰交(さんいんこう):足の内くるぶしから指4本分上にあるツボで、婦人科系の症状全般に効果があります。
- 太渓(たいけい):足の内くるぶしの後ろのくぼみにあるツボで、腎の機能を高め、骨盤周辺の痛みを改善します。
- 足三里(あしさんり):膝の下外側にあるツボで、全身の気を補い、疲労回復に効果があります。
- 合谷(ごうこく):手の親指と人差し指の骨が交わるあたりにあるツボで、全身の気の流れを調整します。
これらのツボはあくまで一例で、実際の施術では、お一人おひとりの体質や証、症状の程度に合わせて最適なツボを選択し、施術を行います。
恥骨の痛みに関するよくある質問(FAQ)
症状の程度や期間、体質によって個人差がありますが、一般的には以下のような目安があります:
- 急性期(発症から1ヶ月以内):週2回の頻度で1〜2ヶ月
- 慢性期(発症から3ヶ月以上):週1〜2回の頻度で2〜3ヶ月
- 妊娠中の症状:週1回の頻度で症状の改善まで継続
初回の施術の前に、あなたの状態に合わせた通院計画をご提案いたします。症状の改善に合わせて、徐々に通院間隔を広げていくことが一般的です。継続的な施術により、根本的な体質改善を目指します。
はい、妊娠中でも安全に施術を受けることができます。当院では、妊娠期の恥骨の痛みに対して以下のような安全な施術を行っています:
- 妊娠期に禁忌とされるツボを避けた安全な鍼灸治療
- うつ伏せにならない、側臥位での優しい施術
- お腹に負担をかけない骨盤調整
- 妊娠期の体質変化に合わせた個別的なアプローチ
妊娠中の恥骨の痛みは、胎児の成長とともに悪化することが多いため、早期の対処が重要です。施術前には必ず現在の妊娠週数や体調についてお聞きし、最も安全で効果的な施術を提供いたします。
はい、恥骨の痛みと腰痛には密接な関係があります。以下のような関連性があります:
- 骨盤帯痛症候群:恥骨の痛みは骨盤帯痛症候群の一部として、腰痛や仙腸関節痛と同時に現れることがあります
- 代償的な動作:恥骨の痛みをかばうような歩き方や姿勢により、腰部に負担がかかり腰痛が発生します
- 筋肉の連鎖:恥骨周辺の筋肉と腰部の筋肉は機能的に関連しており、一方の問題が他方に影響します
- 骨盤の不安定性:恥骨結合部の不安定性は、腰椎や仙腸関節にも影響を与えます
当院では、恥骨の痛みと腰痛を関連する症状として捉え、骨盤全体のバランスを整える施術を行います。単独の症状を治療するのではなく、全身のバランスを考慮した根本的な改善を目指します。
恥骨の痛みがある時は、以下のような動作を避けることで症状の悪化を防ぐことができます:
- 片足立ちになる動作:階段昇降、ズボンの着脱、靴下の着脱など
- 足を大きく開く動作:跨ぐ、あぐらをかく、足を組むなど
- 重いものを持ち上げる動作:腹圧がかかり恥骨への負担が増します
- 急激な方向転換:スポーツや歩行時の急な方向転換
- 長時間の同一姿勢:長時間の立位や座位
これらの動作を行う際は、両足に均等に体重をかける、手すりを使用する、膝を曲げて物を持ち上げるなどの工夫をしましょう。当院では、日常生活での注意点について詳しくアドバイスいたします。
施術後は以下の点にご注意いただくと、効果を最大限に引き出すことができます:
- 施術当日は激しい運動や長時間の歩行を避ける
- 十分な水分を摂取し、体内の循環を促進させる
- 恥骨周辺を冷やさないよう注意し、必要に応じて温める
- 指導された姿勢や動作の注意点を守る
- 十分な睡眠と休息を取る
また、稀に施術後に一時的に症状が変化することがありますが、これは体が調整されていく過程で起こる好転反応の一種です。通常は24〜48時間以内に収まりますが、気になる症状がある場合は院長にご相談ください。
恥骨の痛み改善のための自宅でのセルフケア
恥骨の痛みの改善には、施術と併せて日常生活での取り組みも重要です。以下のセルフケア方法を継続的に行うことで、症状の緩和と再発防止につながります。
姿勢の意識
- 立位姿勢:両足に均等に体重をかけ、骨盤を正しい位置に保ちます。反り腰や猫背にならないよう注意しましょう。
- 座位姿勢:深く腰掛け、背もたれを利用して腰椎の自然なカーブを保ちます。足は床にしっかりとつけましょう。
- 歩行姿勢:小幅で歩き、急激な方向転換を避けます。階段は一段ずつゆっくりと昇降しましょう。
- 寝る姿勢:横向きで寝る際は膝の間にクッションを挟み、仰向けの場合は膝の下にクッションを置くと楽になります。
簡単ストレッチ
- 骨盤傾斜運動:仰向けに寝て膝を立て、腰を床に押し付けるように骨盤を後傾させます。5秒間キープを10回繰り返します。
- 内転筋ストレッチ:座った状態で足裏を合わせ、膝を軽く床に近づけます。無理をせず、痛みの出ない範囲で行いましょう。
- 股関節屈筋ストレッチ:片膝を床につき、もう一方の足を前に出してゆっくりと体重をかけます。左右30秒ずつ行います。
- 膝抱えストレッチ:仰向けに寝て片膝を胸に引き寄せます。30秒間キープし、左右交互に行います。
ツボ押し
自分でできるツボ押しも効果的です。以下のツボを親指や人差し指で3〜5秒間押し、緩めるを10回程度繰り返しましょう:
- 三陰交(さんいんこう):足の内くるぶしから指4本分上にあるツボです。婦人科系の症状全般に効果があります。
- 太渓(たいけい):足の内くるぶしの後ろのくぼみにあるツボです。腎の機能を高め、骨盤周辺の痛みを和らげます。
- 足三里(あしさんり):膝の下外側にあるツボです。全身の気を補い、疲労回復に効果があります。
- 合谷(ごうこく):手の親指と人差し指の付け根にあるツボです。全身の気の流れを良くし、痛みの緩和に効果があります。
温熱療法
- 湯船にゆっくり浸かる:38〜40度のぬるめのお湯に15〜20分浸かることで、骨盤周辺の血流を改善します。
- 湯たんぽ・カイロの使用:腰やお腹に湯たんぽやカイロを当てて温めることで、筋肉の緊張を和らげます。
- 足湯:足首まで温かいお湯に浸けることで、下半身の血行を促進します。
- 蒸しタオル:温かい蒸しタオルを恥骨周辺(直接ではなく下着の上から)に当てて温めます。
生活習慣の改善
- 食事の改善:抗炎症作用のある食材(青魚、緑黄色野菜、ナッツ類など)を積極的に摂り、糖質や揚げ物、甘い物は控えめにしましょう。
- 水分摂取:十分な水分を摂ることで、体内の循環を促進し、老廃物の排出を促します。
- 規則正しい睡眠:7〜8時間の質の良い睡眠を心がけ、体の回復を促進します。
- ストレス管理:深呼吸、瞑想、軽い運動などでストレスを軽減し、筋肉の緊張を和らげます。
- 適度な運動:水中ウォーキングやヨガなど、関節に負担の少ない運動を無理のない範囲で行います。
これらのセルフケアを日常生活に取り入れることで、施術の効果を高め、恥骨の痛みの改善と再発防止につながります。無理なく続けられる方法から始めて、徐々に習慣化していきましょう。
恥骨の痛みのまとめと施術のご案内
恥骨の痛みの要約
恥骨の痛みは、恥骨結合部やその周辺の筋肉、靭帯に炎症や負担がかかることで発生する症状です。特に妊娠中や産後の女性に多く見られますが、スポーツ選手や日常的な姿勢の問題により男性にも起こることがあります。
西洋医学では恥骨結合部の機能不全や筋肉の不均衡に着目し、東洋医学では気血の滞りや腎肝の機能低下と捉えて治療にあたります。どちらのアプローチも長所があり、当院ではこれらを組み合わせた総合的な治療を提供しています。
恥骨の痛みは早期に適切な対処を行うことで、多くの場合改善が期待できます。しかし、治療だけでなく、日常生活での姿勢改善、適切な動作方法、セルフケアなども重要です。当院では、施術と生活指導の両面からサポートし、根本的な改善と再発防止を目指しています。
当院のアプローチの特徴
当院では、恥骨の痛みに対して以下のようなアプローチを行っています:
- 東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた総合的な施術
- 一人ひとりの体質や症状に合わせたオーダーメイドの治療計画
- 妊娠期にも安全な手足のツボを使った鍼灸治療
- 骨盤の調整と全身のバランスを整える優しい整体
- 症状の緩和だけでなく、根本的な体質改善と再発防止を目指した施術
多くの患者様から「恥骨の痛みが軽減した」「歩くのが楽になった」「寝返りが痛くなくなった」「妊娠中も安心して治療を受けられた」といったお声をいただいております。恥骨の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご予約・お問い合わせ
恥骨の痛みの症状でお悩みの方は、ぜひ当院までご連絡ください。初回のカウンセリングで丁寧にお話を伺い、最適な施術プランをご提案いたします。
【住所】
567-0818
大阪府茨木市本町1-16本町8番館1階
(阪急茨木市駅から徒歩5分)
【お電話】
072-622ー0134
【受付時間】
月・火・木・金 10:00~13:30 16:00~19:30
水・土 10:00~13:30
日曜・祝日 休み
恥骨の痛みは適切なケアで必ず改善できます。当院では、あなたの恥骨の痛みの根本改善をサポートし、健やかな日常生活を取り戻すお手伝いをいたします。
施術料 6600円(税込)
初診料 1100円(税込)
(前回の施術から2ヶ月以上空いた場合は1100円を頂いております)
※クレジットカード、QRコード払い等、各種キャッシュレス決済に対応しております。
ご予約はこちら
ネット予約:
LINEで予約:
電話で予約:
072-622-0134
円(税込)初診料 1100円(税込)
(前回の施術から2ヶ月以上空いた場合は1100円を頂いております)
※クレジットカード、QRコード払い等、各種キャッシュレス決済に対応しております。
ご予約はこちら
ネット予約:
LINEで予約:
電話で予約:
072-622-0134