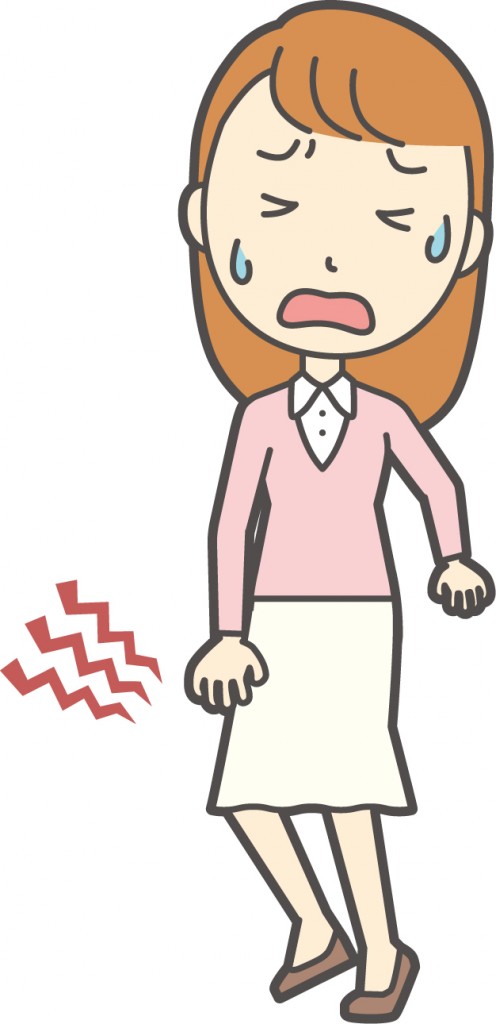群発頭痛
こんなお悩みはありませんか?
もしあなたが
- どこに行っても良くならない
- 検査を受けてもどこも悪くないと言われる
- 何が原因なのかはっきりしない
- できれば薬に頼りたくない
- 強いマッサージやボキボキする整体は避けたい
などでお困りなら、
茨木市で開院して27年(1996年開院)、
多くの実績を積み上げた当院がお役に立てます。
あなたと同じ悩みを抱えていた患者さんも
今では健康な日常生活を取り戻し、やりたいことに
思いっきり取り組めるようになっているからです。
院長プロフィール
羽田雄作。はだ鍼灸整骨院院長。
1965年生まれ。兵庫県淡路市出身。
幼少期はすぐに熱を出したり、お腹をこわすなどして
自身の体力に自身が持てなかった。
それを鍼灸で治そうとする父、病院を受診させようとする母、
食事で改善しようとする祖母の三者三様の手当を受け、虚弱体質を脱する。
姉や兄が治療を受ける姿を見たり、親子・兄弟で操体法に取り組んだ経験もあり、
東洋医学に興味を持つのは自然の成り行きであった。
1987年に鍼灸師、1990年に柔道整復師の資格を取得。
大阪市内で複数の鍼灸整骨院に勤めたあと1996年、茨木市にて
「はだ鍼灸整骨院」を開院。
自律神経の調整、血流の改善を目的とした独自の鍼灸・整体は、
開院以来27年以上に渡り多くの支持を得ている。
群発頭痛とは
群発頭痛に対する当院の施術
患者様の声
群発頭痛について簡単に説明いたしました。
群発頭痛の施術を検討されている方は、
ぜひ一度当院の鍼灸・整体をご検討ください。
当院では、群発頭痛の施術に豊富な経験と実績を持つ私が、
一人ひとりの症状に合わせて丁寧に施術いたします。
まずは、お気軽にご相談ください
はだ鍼灸整骨院のご案内
567-0818
茨木市本町1-16本町8番館1階
(阪急茨木市駅より徒歩5分)
時間 10:00~13:30
16:00~19:30
水曜・土曜は13:30まで受付
日曜・祝日は休み
ご予約はこちらから
電話 072-622-0134
「ホームページを見て」とお電話ください。
ネット予約 https://www.ekiten.jp/shop_590373/reserve/
LINE 「はだ鍼灸整骨院」を検索、「友だちを追加」で
ご希望の日時をお伝えください。