脊柱側弯症
茨木市で脊柱側弯症でお悩みの方へ
こんなお悩みはありませんか?
- 背中や腰に曲がりがあると指摘されたことがある
- 左右の肩の高さが違っている
- 肋骨や背中に左右差があり、体の歪みが気になる
- 腰痛や背中の痛みが慢性的に続いている
- 息苦しさや疲れやすさを感じることがある
- 学校や職場の健康診断で側弯症の疑いを指摘された
脊柱側弯症は、背骨の歪みによって起こる症状で、背骨が正面から見て左右に曲がっている状態をいいます。成長期に発見されることが多いですが、大人になってから症状が現れたり悪化したりすることもあります。
この記事では、脊柱側弯症の原因を西洋医学と東洋医学の両面から解説し、根本的な改善方法についてご紹介します。当院の鍼灸治療がどのように脊柱側弯症の症状を緩和し、姿勢改善に導くのか、また自宅でできるセルフケアの方法についても詳しくお伝えしていきます。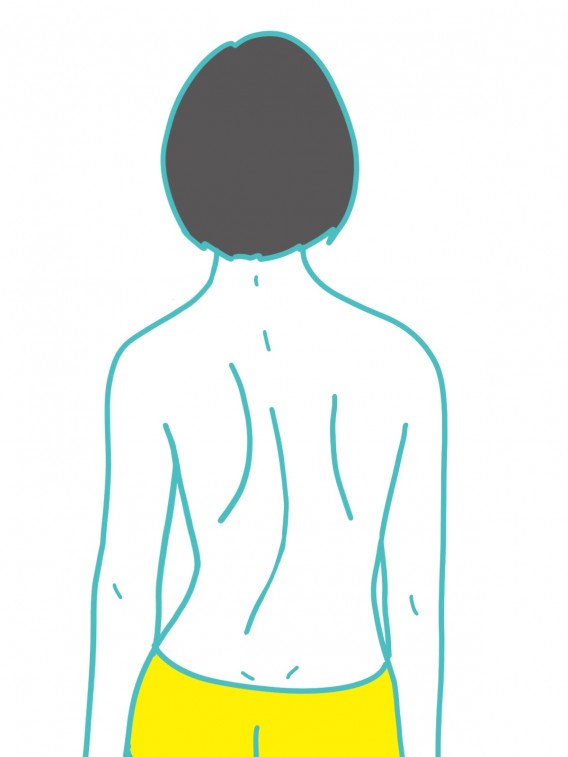
西洋医学の視点から脊柱側弯症の原因とメカニズム
脊柱側弯症とは
西洋医学では、脊柱側弯症は「背骨が正面から見て左右に10度以上曲がった状態」と定義されています。正常な脊椎は正面から見るとまっすぐですが、横から見ると頸部と腰部で前に、胸部では後ろに緩やかなカーブを描いています。脊柱側弯症では、このような正常な構造に加えて、左右への曲がりが生じます。
主な原因
- 特発性側弯症:全体の約80%を占める原因不明の側弯症で、成長期の女子に多く見られます。遺伝的要因が関与していると考えられています。
- 先天性側弯症:生まれつき椎体や肋骨の形成異常により起こる側弯症です。
- 神経筋原性側弯症:神経や筋肉の病気(脳性麻痺、筋ジストロフィーなど)が原因で起こる側弯症です。
- 変性側弯症:加齢により椎間板や関節が変性し、大人になってから発症または進行する側弯症です。
- 機能性側弯症:脚の長さの違いや筋肉の緊張などによる一時的な側弯で、原因を除去すると改善します。
脊柱側弯症が発生するメカニズム
脊柱側弯症は以下のようなメカニズムで発生します:
- 成長期において、脊椎の成長に不均衡が生じ、椎体の一側が他方より早く成長することで側弯が始まります
- 側弯が進行すると、椎体は楔形に変形し、椎間板にも変性が生じます
- 脊椎の左右への曲がりに加えて、椎体の回転(ねじれ)も生じ、肋骨の変形も伴います
- 側弯が進行すると、胸郭(胸の骨格)の変形により、心肺機能に影響を及ぼすことがあります
- また、脊椎周囲の筋肉バランスが崩れることで、慢性的な腰痛や背中の痛みが生じることがあります
主な症状
- 外見上の変化:肩の高さの左右差、肩甲骨の突出、ウエストラインの非対称、肋骨の隆起などが見られます。
- 腰痛・背中の痛み:筋肉のバランス異常により、慢性的な痛みが生じることがあります。
- 疲労感:姿勢を維持するために筋肉に過度な負担がかかり、疲れやすくなります。
- 呼吸困難:重度の場合、胸郭の変形により肺機能が低下し、息苦しさを感じることがあります。
- 心機能への影響:非常に重度の場合、心臓への圧迫により心機能に影響を及ぼすことがあります。
- 神経症状:脊椎の変形により神経が圧迫されると、手足のしびれや筋力低下が生じることがあります。
西洋医学的なアプローチでは、側弯の程度に応じて経過観察、装具療法、手術療法などが選択されます。また、理学療法による筋力トレーニングや姿勢改善も重要な治療法とされています。
東洋医学の視点から脊柱側弯症の原因とメカニズム
東洋医学での脊柱側弯症の捉え方
東洋医学では、脊柱側弯症を「脊柱偏歪」「筋骨失調」などと表現し、「腎精の不足」「督脈の機能低下」「筋骨の発育不良」によって起こる状態と捉えます。背骨は「督脈」という重要な経絡が通る部位であり、この経絡の機能低下や気血の不調和により脊椎の正常な発育や維持が困難になると考えられています。
関連する経絡
脊柱側弯症に特に関連する経絡には以下のようなものがあります:
- 督脈(とくみゃく):背骨の中央を通る重要な経絡で、脊椎の構造と機能を支配します。
- 足の太陽膀胱経(たいようぼうこうけい):背中の両側を走る経絡で、脊椎を支える筋肉群に関わります。
- 足の少陽胆経(しょうようたんけい):体側を通る経絡で、側弯症の左右のバランス調整に関係します。
- 足の太陰脾経(たいいんひけい):筋肉の栄養と発育に関わり、筋力バランスに影響します。
- 足の少陰腎経(しょういんじんけい):骨の成長と発育を司り、先天的体質に関わります。
東洋医学の「証」による分類
東洋医学では、脊柱側弯症を以下のような「証」(体質や症状のパターン)に分類します:
1. 腎精不足(じんせいぶそく)
特徴:先天的な腎精の不足により、骨や筋肉の発育が不十分な状態です。
症状:成長期の発育不良、骨がもろい、筋力が弱い、疲れやすい、腰膝がだるい。
改善方法:腎精を補う補腎の治療が効果的です。
2. 気血不足(きけつぶそく)
特徴:気血の生成や循環が不足し、筋骨の栄養が不十分な状態です。
症状:顔色が悪い、疲れやすい、筋力が弱い、食欲不振、めまい、動悸。
改善方法:気血を補う補気養血の治療が効果的です。
3. 督脈虚弱(とくみゃくきょじゃく)
特徴:督脈の機能が低下し、脊椎を支える力が不足した状態です。
症状:背骨がまっすぐ保てない、背中の痛み、頭がふらつく、記憶力低下。
改善方法:督脈を温めて強化する温督脈の治療が効果的です。
4. 肝腎陰虚(かんじんいんきょ)
特徴:肝と腎の陰液が不足し、筋骨の柔軟性が失われた状態です。
症状:筋肉が硬い、関節の可動域が狭い、イライラしやすい、目の疲れ、腰痛。
改善方法:肝腎の陰を補う滋陰の治療が効果的です。
5. 脾腎陽虚(ひじんようきょ)
特徴:脾と腎の陽気が不足し、筋肉の力と温煦機能が低下した状態です。
症状:冷え症、むくみ、筋力低下、下痢しやすい、腰が冷える。
改善方法:脾腎の陽気を温める温陽の治療が効果的です。
五臓六腑との関連性
東洋医学では、脊柱側弯症は主に以下の臓腑の機能と関連しています:
- 腎(じん):骨の成長と発育を主管し、先天的な体質の基盤となります。腎の機能低下は骨格の異常を引き起こしやすくします。
- 肝(かん):筋肉や腱を養い、体の柔軟性を保ちます。肝の機能低下は筋肉の緊張や関節の硬さにつながります。
- 脾(ひ):気血を生成し、筋肉の栄養を担当します。脾の機能低下は筋力の低下や発育不良を引き起こします。
- 肺(はい):気を全身に巡らせ、姿勢を保持する役割があります。肺の機能低下は姿勢の維持に影響します。
- 心(しん):血液循環を司り、筋骨の栄養供給に関わります。心の機能低下は組織の栄養不良を招きます。
成長期と環境の影響
東洋医学では、成長期の環境や生活習慣も脊柱側弯症の発症や進行に影響すると考えます:
- 成長期(思春期):腎精が急激に変化する時期で、骨格の成長が不安定になりやすい時期です。
- 栄養不足:脾胃の機能低下により栄養吸収が悪くなると、筋骨の発育に影響します。
- 運動不足:気血の流れが滞り、筋肉の発達が不十分になります。
- 不良姿勢:長時間の悪い姿勢は経絡の流れを妨げ、側弯を悪化させることがあります。
- 精神的ストレス:肝気鬱結により筋肉の緊張が増し、姿勢バランスに影響を与えます。
東洋医学では、このように体質や成長段階、環境などの要因を総合的に考慮し、一人ひとりに合わせた治療方針を立てていきます。
西洋医学と東洋医学の比較
| 比較項目 | 西洋医学 | 東洋医学 |
|---|---|---|
| 病名・呼称 | 脊柱側弯症、側彎症 | 脊柱偏歪、筋骨失調 |
| 原因の捉え方 | 遺伝的要因、成長期の椎体成長不均衡、神経筋疾患、先天異常 | 腎精不足、督脈虚弱、気血不足、肝腎の機能失調 |
| 診断方法 | X線撮影(コブ角測定)、MRI、CT、理学的検査 | 四診(望診・聞診・問診・切診)、体質・証の判断 |
| 治療アプローチ | 経過観察、装具療法、理学療法、手術療法 | 鍼灸治療、漢方薬、推拿、体質改善、養生指導 |
| 治療の焦点 | 側弯角度の進行抑制、構造的改善、機能改善 | 全身の気血調和、臓腑機能改善、筋骨バランス調整 |
| 治療目標 | 側弯の進行防止、症状緩和、機能維持 | 体質強化、自然治癒力向上、症状改善と予防 |
| 個人差の考慮 | 側弯の程度や部位、年齢に基づいた治療選択 | 個人の体質・証に基づいたオーダーメイド治療 |
| 予防の考え方 | 早期発見・早期治療、運動療法、姿勢指導 | 体質改善による根本予防、未病治療、養生法 |
西洋医学と東洋医学はそれぞれ異なる視点から脊柱側弯症にアプローチしますが、どちらも重要な役割があります。当院では両方の知見を活かしながら、お一人おひとりに最適な治療を提供しています。
脊柱側弯症を放置するリスク
脊柱側弯症は「見た目の問題だけ」と思われがちですが、適切な対処をしないまま放置すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。
身体的リスク
- 側弯の進行:特に成長期では、放置すると側弯角度が急速に進行し、より重篤な状態になるリスクがあります。
- 呼吸機能の低下:重度の胸椎側弯により胸郭が変形し、肺機能が低下して呼吸困難を来すことがあります。
- 心機能への影響:極度の胸椎側弯では、心臓が圧迫され、心機能に影響を及ぼす可能性があります。
- 慢性腰痛・背中の痛み:筋肉バランスの異常により、慢性的な痛みが続くようになります。
- 神経障害:脊椎の変形が進むと神経が圧迫され、手足のしびれや筋力低下が生じることがあります。
- 消化機能への影響:腹部の変形により、内臓が圧迫され、消化不良や便秘などが起こることがあります。
- 関節炎:異常な負荷により、脊椎や骨盤の関節に変形性関節症が生じやすくなります。
精神的・社会的リスク
- 自己肯定感の低下:外見の変化により、自信を失ったり、人前に出るのを避けるようになることがあります。
- 社会活動の制限:運動や日常生活動作が制限され、友人関係や社会参加に影響が出ることがあります。
- 学業・仕事への影響:痛みや疲労により、集中力の低下や学業・仕事のパフォーマンス低下が起こることがあります。
- うつ症状:慢性的な痛みや外見の変化により、気分の落ち込みやうつ症状が現れることがあります。
- 将来への不安:病気の進行や将来の生活に対する不安が強くなることがあります。
早期対処の重要性
脊柱側弯症は、早期に適切な対処を行うことで、進行を抑制し、症状を改善することが可能です。早期対処には以下のようなメリットがあります:
- 成長期であれば進行を効果的に抑制できる可能性が高い
- 軽度のうちに対処することで、より侵襲的な治療を避けられる
- 筋肉バランスの改善により、痛みや不快感を軽減できる
- 呼吸機能や心機能への影響を予防できる
- 心理的負担を軽減し、生活の質を維持できる
- 将来の健康リスクを大幅に減らすことができる
背骨の歪みや肩の高さの違い、腰痛などの症状に気づいたら、「成長すれば治る」「軽度だから大丈夫」と思わずに、早めに専門家に相談することをおすすめします。
当院の脊柱側弯症施術方法
当院では、東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた独自のアプローチで脊柱側弯症の根本改善を目指します。一人ひとりの症状や体質に合わせたオーダーメイドの施術を行い、背骨の歪みの改善と筋肉バランスの調整、姿勢改善を促進します。
施術の特徴
- 手足のツボを使った鍼灸治療:身体に負担の少ない施術で、自然治癒力を高めながら側弯症改善を促します。
- 東洋医学的診断に基づくアプローチ:脈診や舌診などで体質を見極め、根本原因にアプローチします。
- 督脈と膀胱経の調整:背骨に関わる重要な経絡の流れを整え、脊椎機能の改善を図ります。
- 筋バランス調整:左右の筋肉バランスを整える整体施術を組み合わせます。
- 体質改善:腎精を補い、成長期の発育をサポートし、大人では組織の再生力を高めます。
施術の流れ
- 問診:側弯症の発症時期、症状、生活習慣、既往歴などを詳しくお聞きします。
- 東洋医学的診断:脈診・舌診・体型観察などを通じて、あなたの体質や「証」を判断します。
- 整体施術:背骨や骨盤の調整、筋肉バランスの改善を行います。
- 鍼灸治療:あなたの体質や症状に合わせたツボに鍼をし、必要に応じてお灸を行います。
- アフターケア:日常生活での注意点や、自宅でできるエクササイズについてアドバイスします。
脊柱側弯症に効果的なツボ
当院では以下のようなツボを用いて、お一人おひとりの症状に合わせた治療を行います:
手足のツボ(遠隔治療)
- 腎兪(じんゆ):手足にある腎機能を高めるツボで、骨の成長と発育をサポートします。
- 太渓(たいけい):足の内くるぶしの後ろにあるツボで、腎精を補い、骨を強くします。
- 足三里(あしさんり):膝の下外側にあるツボで、脾胃の機能を高め、筋肉の栄養を改善します。
- 外関(がいかん):手首から指3本分上の腕の外側にあるツボで、筋骨のバランスを調整します。
- 陽陵泉(ようりょうせん):膝の外側下方にあるツボで、筋肉の緊張を和らげ、側弯に関わる筋肉バランスを改善します。
これらのツボはあくまで一例で、実際の施術では、お一人おひとりの体質や証、症状の程度、年齢などに合わせて最適なツボを選択し、施術を行います。
脊柱側弯症に関するよくある質問(FAQ)
脊柱側弯症の改善度合いは、側弯の程度、年齢、原因、体質などによって個人差があります。鍼灸治療では、構造的な変化を完全に元に戻すことは困難ですが、以下の効果が期待できます:
- 筋肉バランスの改善により、姿勢改善と痛みの軽減
- 成長期では側弯の進行抑制
- 呼吸機能の改善と疲労感の軽減
- 体質改善による自然治癒力の向上
特に軽度から中度の側弯症では、鍼灸治療により症状の大幅な改善が期待できます。重度の場合でも、症状の緩和や生活の質の向上に効果があります。
治療期間は側弯の程度、年齢、体質によって大きく異なりますが、一般的には以下のような目安があります:
- 軽度の側弯症(成長期):週1〜2回、3〜6ヶ月
- 中度の側弯症:週1〜2回、6ヶ月〜1年
- 成人の側弯症:週1回、6ヶ月〜継続的なケア
初回の施術の前に、あなたの状態に合わせた治療計画をご提案いたします。成長期の場合は進行抑制が重要なため、集中的な治療が必要です。成人の場合は症状管理と生活の質向上を目指し、継続的なケアをおすすめします。
はい、成長期を過ぎた成人の脊柱側弯症でも、鍼灸治療による効果は十分期待できます:
- 症状の改善:腰痛、背中の痛み、疲労感の軽減
- 機能改善:呼吸機能、姿勢、可動域の改善
- 進行予防:加齢による側弯の進行抑制
- 生活の質向上:日常生活動作の改善、精神的な安定
成人では骨格的な変化は期待できませんが、筋肉バランスや姿勢の改善により、症状の大幅な軽減が可能です。また、東洋医学的な体質改善により、長期的な健康維持にも寄与します。
はい、装具療法と鍼灸治療は併用することが可能で、相乗効果が期待できます:
- 装具の効果向上:筋肉バランスを改善することで、装具の矯正効果を高めます
- 装具による不快感軽減:装具装着による筋肉の緊張や痛みを和らげます
- 体質改善:成長期の体質を整え、装具療法の効果を最大化します
- 心理的サポート:装具に対する心理的負担を軽減し、治療継続をサポートします
装具を使用されている場合は、初回カウンセリング時にその旨をお伝えください。装具と鍼灸治療を併用することで、より効果的な側弯症改善が期待できます。
脊柱側弯症があっても、適切な運動は症状の改善に有効です。ただし、側弯の程度や症状によって推奨される運動は異なります:
- 推奨される運動:水泳、ウォーキング、ヨガ、ピラティス、バランス運動
- 注意が必要な運動:激しい回転運動、重量挙げ、コンタクトスポーツ
- 個別評価が必要:バレエ、体操、テニス、ゴルフなど左右非対称な運動
当院では、あなたの側弯の状態に応じて、適切な運動やスポーツについてアドバイスいたします。また、鍼灸治療により筋肉バランスを改善することで、より安全に運動を楽しむことができるようになります。
脊柱側弯症改善のための自宅でのセルフケア
脊柱側弯症の改善には、施術と併せて日常生活での取り組みも重要です。以下のセルフケア方法を継続的に行うことで、症状の改善と進行予防につながります。
姿勢の意識
- 正しい立ち姿勢:壁に背中をつけて、後頭部、肩甲骨、お尻、かかとが壁につく姿勢を意識しましょう。
- 座位姿勢:椅子に深く座り、背もたれに背中をつけて、両足を床にしっかりつけましょう。
- デスクワーク時の注意:パソコン画面は目線の高さに設定し、肘は90度を保ちます。
- 荷物の持ち方:重い荷物は両手に分散して持つか、バックパックを使用しましょう。
簡単ストレッチ
- 側屈ストレッチ:立位または座位で、凸側(膨らんでいる側)へゆっくりと体を倒し、凹側(へこんでいる側)の筋肉を伸ばします。
- 回旋ストレッチ:椅子に座り、背筋を伸ばして左右にゆっくりと体をねじります。
- 胸郭ストレッチ:両手を背中で組み、肩甲骨を寄せながら胸を開きます。
- 背中のストレッチ:猫のポーズで背中を丸めたり反らせたりして、脊椎全体の柔軟性を高めます。
筋力トレーニング
- コアトレーニング:プランクや腹筋運動で体幹を強化し、脊椎をサポートします。
- 背筋強化:うつ伏せで上体を軽く持ち上げる背筋運動を行います。
- 臀筋エクササイズ:ブリッジやクラムシェルで臀筋を鍛え、骨盤の安定化を図ります。
- バランス運動:片足立ちやバランスボールを使った運動で、体幹の安定性を高めます。
ツボ押し
自分でできるツボ押しも効果的です。以下のツボを親指で3〜5秒間押し、緩めるを10回程度繰り返しましょう:
- 腎兪(じんゆ):腰のくびれの高さで、背骨から指2本分外側にあるツボです。腎機能を高め、骨を強くします。
- 太渓(たいけい):足の内くるぶしの後ろのくぼみにあるツボです。腎精を補い、成長期の発育をサポートします。
- 足三里(あしさんり):膝の下外側にあるツボです。全身の気を補い、筋肉の栄養を改善します。
- 陽陵泉(ようりょうせん):膝の外側下方にあるツボです。筋肉の緊張を和らげ、筋バランスを整えます。
生活習慣の改善
- 栄養バランス:カルシウム、マグネシウム、ビタミンD、たんぱく質など、骨と筋肉の健康に必要な栄養素をバランスよく摂取しましょう。
- 十分な睡眠:成長ホルモンの分泌を促すため、質の良い睡眠を心がけましょう。
- 規則正しい生活:早寝早起きを心がけ、生活リズムを整えます。
- ストレス管理:適度な運動や趣味の時間を設けて、心身のリラックスを図りましょう。
- 定期的な運動:水泳やウォーキングなど、全身を使う有酸素運動を週3回程度行いましょう。
これらのセルフケアを日常生活に取り入れることで、施術の効果を高め、脊柱側弯症の改善と進行防止につながります。無理なく続けられるものから始めて、徐々に習慣化していきましょう。
脊柱側弯症のまとめと施術のご案内
脊柱側弯症の要約
脊柱側弯症は、背骨の歪みによって様々な症状を引き起こす状態です。西洋医学では構造的変化に注目し、東洋医学では気血の不調和や臓腑機能の低下として捉えて治療にあたります。
軽度の場合は外見上の変化や軽い不快感程度ですが、放置すると進行し、呼吸困難や慢性的な痛み、心理的な負担などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。特に成長期では進行が早いため、早期の対処が極めて重要です。
側弯症改善には、専門的な施術と日常生活での姿勢改善、適切な運動療法、栄養管理などの総合的なアプローチが必要です。一時的な対症療法ではなく、根本的な体質改善と筋肉バランスの調整を目指すことが、長期的な健康維持につながります。
当院のアプローチの特徴
当院では、脊柱側弯症に対して以下のようなアプローチを行っています:
- 東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた総合的な施術
- 一人ひとりの年齢、側弯の程度、体質に合わせたオーダーメイドの治療計画
- 手足のツボを使った鍼灸治療と、筋バランスを整える整体
- 成長期では進行抑制、成人では症状改善と機能向上を重視した施術
- 姿勢改善や自宅でできるエクササイズの具体的な指導
多くの患者様から「姿勢が良くなった」「痛みが軽減した」「呼吸が楽になった」「運動能力が向上した」といったお声をいただいております。脊柱側弯症でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご予約・お問い合わせ
脊柱側弯症の症状でお悩みの方は、ぜひ当院までご連絡ください。初回のカウンセリングで丁寧にお話を伺い、最適な施術プランをご提案いたします。
【住所】
567-0818
大阪府茨木市本町1-16本町8番館1階
(阪急茨木市駅から徒歩5分)
【お電話】
072-622ー0134
【受付時間】
月・火・木・金 10:00~13:30 16:00~19:30
水・土 10:00~13:30
日曜・祝日 休み
脊柱側弯症は一人で悩まず、適切なケアで改善が期待できる症状です。当院では、あなたの脊柱側弯症の根本改善をサポートし、健やかな日常生活を取り戻すお手伝いをいたします。
施術料 6600円(税込)
初診料 1100円(税込)
(前回の施術から2ヶ月以上空いた場合は1100円を頂いております)
※クレジットカード、QRコード払い等、各種キャッシュレス決済に対応しております。
ご予約はこちら
ネット予約:
LINEで予約:
電話で予約:
072-622-0134








